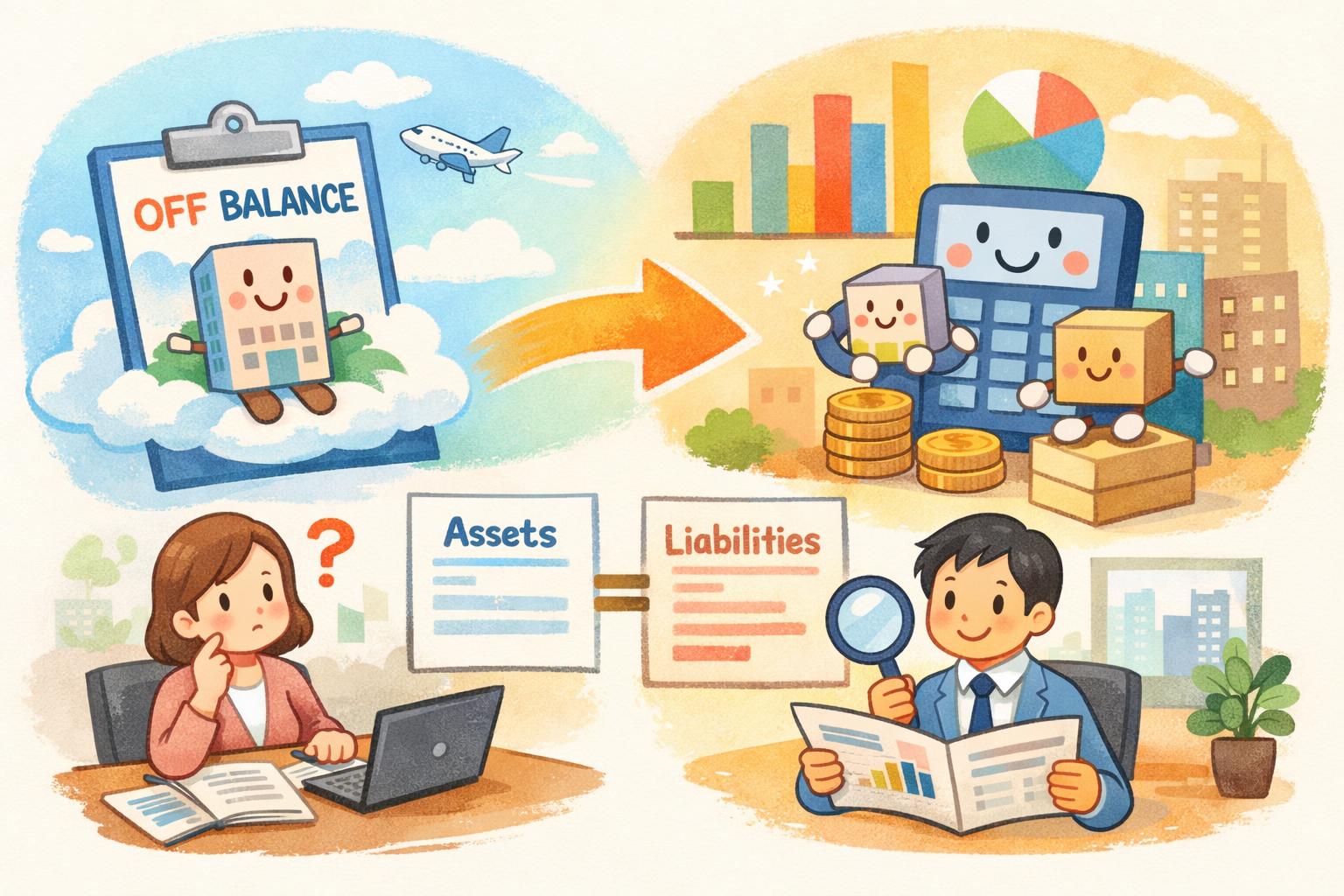「新リース会計基準はいつから適用?」「何が変わって、実務にどう影響するの?」とお悩みの経理・財務担当者の方へ。新リース会計基準の最大の変更点は、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースを含め、すべてのリース取引が原則として資産・負債に計上(オンバランス化)されることです。これにより、企業の財務諸表や経営指標は大きな影響を受けます。本記事では、この複雑な新基準について、適用時期や新旧の変更点を図解でわかりやすく解説。さらに、自己資本比率などへの具体的なインパクトから、経理担当者が今すぐやるべき実務対応までを網羅します。この記事を読めば、新リース会計基準の全体像を正確に理解し、万全の準備を進めることができます。
新リース会計基準とは そもそもリース取引の基本から
2019年に公表された「新リース会計基準」は、これまで国際的な会計基準(IFRS)との差異が指摘されてきた日本のリース会計実務を大きく変えるものです。特に、資産を借りる側である「借手」の会計処理に大きな変更が加えられ、企業の財務諸表に与える影響は少なくありません。この変更を正しく理解するためには、まず「リース取引」そのものの基本と、これまでの会計処理がどのようなものであったかを知ることが不可欠です。この章では、新リース会計基準を学ぶ上での土台となる基礎知識をわかりやすく解説します。
リース取引の定義と種類
リース取引とは、特定の資産(コピー機、PC、自動車、不動産など)の所有者(貸手)が、その資産を使用したいと考える相手(借手)に対し、合意された期間にわたり使用収益権を与え、借手は使用の対価としてリース料を貸手に支払う取引を指します。簡単に言えば「企業向けの長期的なレンタル契約」とイメージすると分かりやすいでしょう。
これまでの会計基準では、リース取引はその経済的な実態に応じて、主に以下の2種類に分類されていました。この分類が、会計処理の方法を決定する上で非常に重要でした。
| リース取引の種類 | 概要 | 具体的な要件 |
|---|---|---|
| ファイナンス・リース取引 | リース契約を途中で解約できず(ノンキャンセラブル)、リース料総額で物件の購入代金と付随費用をほぼ全額回収できる(フルペイアウト)取引。実質的には分割払いで資産を購入するのと同じ経済的実態を持つ取引と見なされます。 | 以下の2つの要件を両方満たすもの。
|
| オペレーティング・リース取引 | ファイナンス・リース取引以外のすべてのリース取引。一般的な賃貸借契約に近い性質を持つ取引です。 | ファイナンス・リースの「ノンキャンセラブル」「フルペイアウト」のいずれか、または両方の要件を満たさないもの。 |
さらに、ファイナンス・リース取引は、リース期間終了後の資産の所有権がどうなるかによって、「所有権移転ファイナンス・リース取引」と「所有権移転外ファイナンス・リース取引」の2つに細分化されます。
これまでのリース会計基準の概要
新リース会計基準を理解するためには、従来の会計基準で上記のリース区分がどのように会計処理されていたかを知ることが重要です。特に借手側の処理の違いがポイントとなります。
従来の会計基準では、リース取引の種類によって「オンバランス処理」と「オフバランス処理」という全く異なる会計処理が適用されていました。
| リース取引の種類 | 従来の会計処理(借手) | 会計処理の概要 |
|---|---|---|
| ファイナンス・リース取引 | オンバランス処理(売買処理) | リース取引の開始時に、貸借対照表(BS)に「リース資産」と「リース負債」を計上します。その後、決算ごとにリース資産の減価償却費と、リース負債にかかる支払利息を損益計算書(PL)に費用として計上します。これは、資産を自己資金や借入金で購入した場合と同様の処理です。 |
| オペレーティング・リース取引 | オフバランス処理(賃貸借処理) | 資産や負債を貸借対照表(BS)に計上しません。毎月支払うリース料を、そのまま「支払リース料」や「賃借料」などの費用として損益計算書(PL)で処理するだけです。このため、リース契約の存在が貸借対照表からは見えにくいという特徴がありました。 |
このように、従来の会計基準では、経済的な実態が似ているにもかかわらず、契約内容のわずかな違いでオペレーティング・リースに分類されると、その契約に関する資産や負債が貸借対照表に計上されない「オフバランス」の状態となっていました。この「簿外債務」の問題は、投資家などが企業の財政状態を正確に把握する上での妨げになると指摘されており、これが新リース会計基準が導入される大きな理由の一つとなったのです。
新リース会計基準はいつから適用されるのか
日本の新しいリース会計基準は、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」や米国会計基準(ASC842号)との整合性を図る目的で開発が進められています。企業会計基準委員会(ASBJ)から公開草案が公表されており、その適用時期の案が示されています。企業の規模や状況によって適用開始のタイミングが異なるため、自社がいつから対応すべきかを正確に把握することが重要です。
上場企業や大会社への適用時期
金融商品取引法の適用を受ける上場企業や、会社法上の大会社などには、原則として新リース会計基準が強制的に適用されます。ただし、準備期間を考慮し、早期適用も認められています。
具体的な適用時期は以下の通りです。
| 区分 | 対象企業(主な例) | 適用開始時期 |
|---|---|---|
| 強制適用 | 金融商品取引法の適用を受ける上場企業およびその連結子会社、会社法上の大会社 | 2026年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から |
| 早期適用 | 上記と同様 | 2024年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から |
強制適用は2026年度からですが、海外に子会社を持つ企業が連結決算の処理を統一するためや、余裕を持った体制構築のために早期適用を選択するケースも考えられます。自社の経営戦略や業務への影響を鑑みて、適用タイミングを慎重に検討する必要があります。
中小企業への影響と適用について
一方で、中小企業については、現時点では新リース会計基準の強制適用は予定されていません。「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠している多くの企業は、引き続き従来の会計処理を継続することが可能です。
中小企業においては、当面の間、従来の会計処理(所有権移転外ファイナンス・リース取引における賃貸借処理など)を継続できるため、直ちに大きな実務変更が発生するわけではありません。
ただし、中小企業であっても、以下のような場合には新基準の任意適用を検討する可能性があります。
- 将来的に株式上場(IPO)を計画している
- 親会社が新リース会計基準を適用しており、グループ全体で会計方針を統一する必要がある
- 金融機関や取引先への説明責任の観点から、財務状況の透明性を高めたい
現状では強制適用ではないものの、会計基準は常に変化する可能性があるため、中小企業の経理担当者も今後の動向を注視しておくことが望ましいでしょう。
【図解】新リース会計基準の重要な変更点 新旧比較で解説
2026年4月以降に開始する事業年度から強制適用が検討されている「新リース会計基準」。その内容は、企業の財務諸表や経営指標に大きな影響を与える可能性があります。特に、これまで費用処理(オフバランス)が認められていたリース契約の多くが、資産・負債として計上(オンバランス)されることになるため、経理担当者は変更点を正確に理解し、早期に準備を進めることが不可欠です。ここでは、新旧の会計基準を比較しながら、重要な変更点を図解も交えてわかりやすく解説します。
最大の変更点 すべてのリースを原則オンバランス化
新リース会計基準における最大の変更点は、借手の会計処理において、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースを含め、すべてのリース取引を原則として貸借対照表(B/S)に資産・負債として計上(オンバランス化)することです。これは、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」と同様の考え方であり、企業の財務実態をより正確に投資家などの利害関係者に示すことを目的としています。この変更により、企業が利用しているリース資産の実態が財務諸表上で明確になります。
使用権資産とリース負債とは
すべてのリースをオンバランス化するにあたり、新たに「使用権資産」と「リース負債」という勘定科目を用いて会計処理を行います。
- 使用権資産
リース期間にわたって原資産(リース物件)を使用する権利を資産として計上するものです。原則として、リース負債の当初測定額に、リース契約締結までにかかった付随費用などを加算して計上します。 - リース負債
リース期間にわたって支払うリース料総額のうち、未払い分を現在価値(将来の支払額を現在の価値に換算したもの)で割り引いて計算した金額を負債として計上します。
つまり、賃貸借契約であるオフィスや社用車、コピー機なども、これまでは費用処理していたものであっても、これからは自社の「資産」と「負債」として貸借対照表に計上する、というイメージになります。
従来のファイナンスリースとオペレーティングリースの区分廃止
従来の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分類し、それぞれ異なる会計処理を行っていました。しかし、新基準では借手においてこの区分が原則として廃止され、単一の会計モデルが適用されます。
| リース区分 | 従来の会計基準 | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| ファイナンス・リース | オンバランス処理 リース資産とリース債務をB/Sに計上 |
原則すべてのリースをオンバランス処理 (区分の廃止) 使用権資産とリース負債をB/Sに計上 |
| オペレーティング・リース | オフバランス処理 支払リース料をP/Lに費用計上するのみ |
この変更により、オペレーティング・リースを多用していた企業では、貸借対照表の資産と負債が両建てで大きく膨らむことになり、財務諸表の見え方が大きく変わる点に注意が必要です。
貸手の会計処理の変更点
借手の会計処理が大きく変わる一方で、貸手(リース会社など)の会計処理については、従来からの大きな変更はありません。貸手は引き続き、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、それぞれの区分に応じた会計処理を行います。これは、貸手側の投資回収の実態を反映するためには、従来の区分を維持することが合理的と判断されているためです。
新基準で例外となるリース取引
「すべてのリースを原則オンバランス化」という大きな方針転換には、実務上の負担を軽減するための例外規定が設けられています。以下のいずれかに該当するリース取引については、重要性が乏しいと判断され、オンバランス化せず、従来通り賃貸借処理(支払リース料を費用計上)を継続することが認められます。
短期リースに関する規定
リース開始日時点でリース期間が12ヶ月以内であるリースは「短期リース」として、簡便的な会計処理が認められます。この場合、使用権資産とリース負債を計上せず、リース料を発生時に費用として計上できます。
ただし、借手が購入オプション(リース期間終了後にその資産を買い取る権利)を有しており、その権利行使が合理的に確実である場合は、短期リースの対象外となるため注意が必要です。
少額リースに関する規定
リース対象となる資産そのものの価値が低いリースは「少額リース」として、簡便的な会計処理が認められます。国際会計基準(IFRS第16号)では、原資産が新品である場合の価額で「5,000米ドル以下」という具体的な金額が目安として示されており、日本の新基準でも同様の考え方が採用される見込みです。
例えば、PC、タブレット端末、事務用の電話機、オフィス家具などが該当する可能性があります。この判定はリース契約ごとではなく、個々の原資産単位で行うことができます。
新リース会計基準が企業に与える影響
新リース会計基準の適用は、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースが原則として資産・負債計上(オンバランス化)されるため、企業の財務諸表や経営指標に大きな影響を及ぼします。ここでは、具体的なインパクトについて詳しく解説します。
財務諸表(BS・PL)へのインパクト
新リース会計基準の最大のポイントは、すべてのリース取引を原則オンバランス化することです。これにより、貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)の表示が大きく変わります。
これまで費用処理のみで済んでいたオペレーティングリースについても、BSの資産の部に「使用権資産」が、負債の部に「リース負債」がそれぞれ計上されることになります。つまり、資産と負債が両建てで増加し、企業のバランスシートが拡大するのです。
損益計算書(PL)への影響も重要です。従来は「支払リース料」として費用計上されていましたが、新基準では、資産計上された「使用権資産」の減価償却費と、「リース負債」に係る支払利息をそれぞれ費用として計上します。費用の総額はリース期間全体で見れば大きく変わりませんが、費用計上のタイミングが変化します。一般的に、リース期間の初期に費用が大きく計上され、期間の経過とともに減少していく傾向があります。
| 項目 | これまでの会計処理(オペレーティングリース) | 新リース会計基準での処理 |
|---|---|---|
| 貸借対照表(BS) | オフバランス(資産・負債に計上されない) | オンバランス(「使用権資産」と「リース負債」を両建てで計上) →総資産が増加する |
| 損益計算書(PL) | 支払リース料を費用計上(通常は定額) | 減価償却費と支払利息を費用計上 →リース期間の初期に費用が厚くなる傾向 |
経営指標(自己資本比率・ROAなど)への影響
財務諸表の表示が変わることで、それを基に算出される経営指標も変動します。特にリース契約の多い企業では、自己資本比率やROAといった主要な経営指標が悪化するように見える可能性があり、金融機関からの借入や株主評価に影響を与えることも考えられます。
主な経営指標への影響は以下の通りです。
| 経営指標 | 影響 | 理由 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 (自己資本 ÷ 総資産) |
低下 | 分母である総資産が「使用権資産」の計上により増加するため。 |
| 負債比率 (負債 ÷ 自己資本) |
上昇 | 分子である負債が「リース負債」の計上により増加するため。 |
| ROA(総資産利益率) (利益 ÷ 総資産) |
低下 | 分母である総資産が増加するため。利益への影響は軽微な場合でも指標は低下する。 |
| EBITDA (税引前利益+支払利息+減価償却費) |
増加 | これまで営業費用だった「支払リース料」が、営業費用項目外の「支払利息」と「減価償却費」に振り替わるため。 |
このように、新リース会計基準は企業の財務状況の実態をより正確に反映させることを目的としていますが、その過程で各種経営指標が変動します。特に、これまでオペレーティングリースを多用して設備投資を行ってきた航空業界、小売業界、運輸業界などは影響が大きくなることが予想されます。自社の財務戦略やIR活動において、これらの指標変動の理由をステークホルダーへ丁寧に説明していくことが求められます。
経理担当者が今すぐやるべき実務対応と準備
新リース会計基準の適用は、経理部門の実務に大きな変革をもたらします。特に、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースも原則として資産・負債計上が必要となるため、影響は広範囲に及びます。基準適用が目前に迫る中、担当者は何をすべきなのでしょうか。ここでは、今すぐ着手すべき3つのステップを具体的かつ詳細に解説します。
社内のリース契約の全体像を把握する
新基準対応の第一歩は、自社が締結しているすべてのリース契約を網羅的に洗い出し、その実態を正確に把握することです。これまでは賃借料として費用処理するだけで済んでいた契約も管理対象となるため、この「棚卸し」作業が極めて重要になります。
具体的には、経理部門だけでなく、総務部が管理するコピー機や社用車、IT部門が管理するサーバーやPC、営業部門が利用する店舗や事務所など、各部署に散在している契約情報を一つ残らず収集する必要があります。契約書をリストアップし、以下の情報を一覧化していきましょう。
- 契約対象の資産(物件)
- 契約開始日と終了日
- リース料(月額・年額)と支払スケジュール
- 更新オプションや解約オプションの有無とその条件
- 所有権移転条項の有無
- 割安購入選択権の有無
この作業で特に注意すべきは、ソフトウェアのライセンス契約や保守サービス契約といった、一見するとリースに見えない契約です。これらの契約に「識別された資産を使用する権利」が含まれている場合、新基準ではリースとして扱われる可能性があります。契約の実態を精査し、新基準の定義に照らしてリースに該当するかどうかを一件ずつ判定していく地道な作業が求められます。
会計方針の決定と業務フローの見直し
リース契約の全体像が把握できたら、次にそれらを新基準に沿って会計処理するための社内ルール、すなわち「会計方針」を決定します。この方針決定が、今後の業務負荷を大きく左右します。
特に重要な検討項目は以下の通りです。
| 検討項目 | 決定すべき内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 例外規定の適用 | 短期リース(12ヶ月以内)や少額リースを適用するか、また少額と判断する金額基準(重要性の基準値)をいくらに設定するかを決定します。 | この例外規定を適用することで、多数の少額なリース契約を資産計上の対象外とし、実務負担を大幅に軽減できる可能性があります。 |
| リース期間の算定 | 契約書上の期間だけでなく、延長オプションや解約オプションの行使可能性を合理的に見積もり、実質的なリース期間をどのように算定するかのルールを定めます。 | リース期間の長さは、使用権資産とリース負債の計上額に直接影響を与えるため、客観的な判断基準が必要です。 |
| 割引率の算定 | リース負債の現在価値を計算するための割引率を決定します。原則は「リースの貸手の計算に用いられている利率」ですが、これが不明な場合は「追加借入利子率」を使用します。この追加借入利子率をどのように算定するかの具体的な方法を定めます。 | 企業の信用力やリース期間に応じて変動するため、算定プロセスの明確化と文書化が不可欠です。 |
これらの会計方針が固まったら、それに基づき業務フローを再構築します。新規契約の締結から、期中の仕訳計上、契約変更時の再測定、決算時の開示情報作成まで、一連のプロセスを見直し、誰が・いつ・何をするのかを明確に規定する必要があります。これにより、業務の標準化と内部統制の強化を図ります。
新リース会計基準に対応するシステム導入の検討
新リース会計基準では、個々のリース契約ごとに使用権資産の減価償却とリース負債の利息計算が必要となり、計算が非常に煩雑になります。契約件数が多い企業にとって、Excelなど手作業での管理には限界があり、計算ミスや属人化、監査対応の負荷増大といったリスクが懸念されます。
そこで、多くの企業が検討するのが「リース管理システム」の導入です。システムを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- リース契約情報の一元管理と検索性の向上
- 使用権資産・リース負債の計算や仕訳の自動化による業務効率化とミス防止
- 契約変更や再測定に伴う複雑な再計算への迅速な対応
- 決算開示に必要な注記情報のスムーズな作成
- 監査法人への説明責任を果たせる、信頼性の高いデータの担保
システム選定にあたっては、自社の既存会計システムとの連携性、導入実績、サポート体制などを総合的に比較検討することが重要です。
固定資産管理のプロシップで実現する効率的なリース管理
リース管理システムの具体的な選択肢として、多くの企業で導入実績があるのが株式会社プロシップの固定資産管理システム「ProPlus」です。このシステムは、新リース会計基準(およびIFRS第16号)に完全準拠したリース管理機能を提供しています。
「ProPlus」を導入することで、これまで解説してきた煩雑な実務対応を効率化できます。契約情報の登録から、複雑な割引率を用いた現在価値計算、償却スケジュールの作成、会計仕訳の自動生成までをワンストップで実行可能です。特に、契約条件の変更に伴うリメジャメント(再測定)にも標準機能で対応しており、手作業ではミスが起こりがちな処理を正確に行えます。
このような専門システムの活用は、単なる業務効率化にとどまりません。経理担当者が煩雑な計算作業から解放され、会計方針の検討や財務分析といった、より付加価値の高い戦略的な業務に集中できる体制を構築するための有効な投資と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、新リース会計基準の概要から適用時期、重要な変更点、そして企業が取るべき実務対応までを解説しました。新基準の最大の結論は、従来のオペレーティングリースを含む「すべてのリース取引を原則として資産・負債に計上(オンバランス化)する」という点です。これは、企業の財務状況をより透明性の高い形で利害関係者に開示し、国際的な会計基準との整合性を図るために導入されます。
この変更により、特にこれまで多くのオペレーティングリースを抱えていた企業では、貸借対照表(BS)上の総資産と負債がともに増加します。その結果、自己資本比率や負債比率、ROA(総資産利益率)といった経営指標に大きな影響が及ぶ可能性があります。上場企業などでは2026年4月1日以後開始する事業年度からの強制適用が迫っており、対応は急務です。
経理担当者は、まず社内のリース契約の全体像を正確に把握し、会計方針を定めた上で、業務フローの見直しや会計システムの導入検討といった準備を早期に開始することが不可欠です。本記事を参考に、計画的な対応を進めていきましょう。
※記事内容は実際の内容と異なる場合があります。必ず事前にご確認をお願いします【PR】関連サイト
株式会社プロシップ
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル 9F
URL:https://www.proship.co.jp/